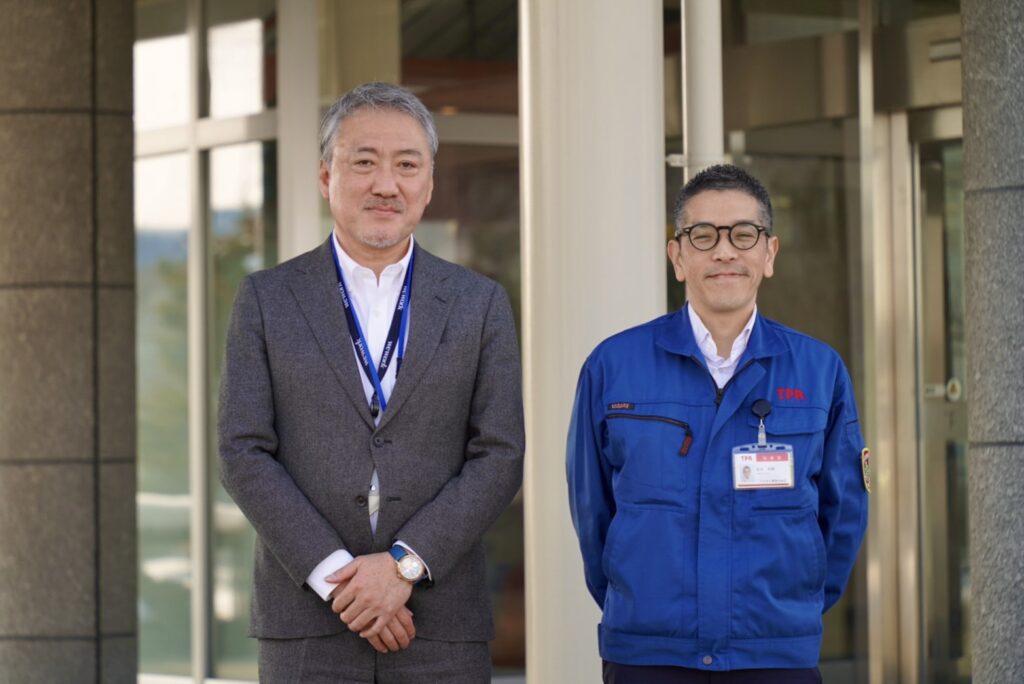
TPR株式会社
執行役員 新事業開発担当 営業部門副担当 塚本英貴 氏(写真左)
受講者 先行開発部 部長 志水利彰 氏(写真右)
- プログラム名:山形大学人材育成プログラム「i-HOPE」2024 新事業創出イノベーションプログラム
- 期間:2024年5月~2024年12月(全17回)
- 対象者:社会人・学生
Q1. 新事業創出に取り組む重要性について教えてください。

塚本氏「今の時代は、既存のサービスだけでなく、新しい課題に目を向け、取り組まないと、売上の拡大や雇用の維持が難しい時代だと感じています。弊社の既存事業の延長線上では、売上の規模や上限が見えてしまい、その結果雇用の維持が困難になります。今ある社会の課題を解決する新たなサービスの創出を目指して取り組むことが、今の時代には必要です。」
Q2. 本プログラムを受講して感じた良かった点について教えてください。

志水氏「新事業創出を検討する際、コンサルタントを入れようかという話になるのですが、コンサルタントは新事業創出の方法を教えてくれることがメインです。しかし、このプログラムでは、教育機関が運営しているので、方法だけでなく、それを実現しようとするそもそものマインドや志向する習慣を身につけることができ、コンサルタントとは異なる価値を実感しました。
また、『新事業を創出するための課題』に対する深掘りをすると、人材育成という『教育』に行きつくと思います。本プログラムはまさに『新事業創出するための課題』に対して、真に深掘りをした教育活動でした。全国でもアントレプレナーシップを学べる取り組みは増えていますが、本プログラムはその先駆け的な存在だと感じました。」
Q3. 本プログラムを通して、どんな学びや気づきがありましたか?

志水氏「縁の下の力持ちとして、上司や管理部門など準備する人が重要だと感じました。社員一人一人に自分の仕事がありますが、チームに共通の課題を設定し、今回の講師の方々のようなフォローする役割の人がいれば、チームで結束し取り組みを進めていけると感じました。
また、開発をしていると、自分のアンテナが『差別化』や『競合技術との違い』に目を向けがちになりますが、他のアンテナも立てておかなければならないと感じました。今回、講師やメンターの方々から反対意見や厳しい意見を受ける中で、それらをアドバイスと捉えることで、チームの結束力が強まり、アイディアに深みが出て、さらに価値の提供が広がる可能性があると実感しました。」
Q4. 最終発表で最高の審査点でしたが、チームが上手くいった要因は何でしょうか?

志水氏「要因の一つは、メンバーが人の話を聞く姿勢を持っていたことです。講師の方もおっしゃっていましたが、人の意見を理解してから発言することができたので、チームが上手く機能しました。
もう一つは、自分の意見を発信することが得意なメンバーが多かったことです。その中で、私が取り組んだことは、皆さんのキャラクターを最大限に活かせる領域を見つけることでした。例えば、事業系の分野は銀行の方、ロジックの部分はソフトウェアの方、といった具合に、グループワークを通じて得意分野が明確になり、メンバーの特徴を生かして進めることができたのが良かったのだと思います。」
Q5. 講義後に実施していた「ルーブリック*」には、どのような効果を感じましたか?

志水氏「ルーブリックの項目を、次の講義までに『あるべき姿』として実践することを心掛けた結果、目に見える成果が得られました。講義の4~5回目あたりから、周囲のメンバーも自然とルーブリックに記載された指標を意識した行動を取るようになり、効果を発揮していると強く実感しました。ルーブリックで明確に示された項目が、受講者の理想像を可視化し、それを意識することで、自分自身の成長を促せたのだと思います。」
塚本氏「このルーブリックの仕組みは、ぜひ社内でも取り入れてみたいですね。ルーブリックで示された目標を目指すプロセスを通じて、従業員の意識や行動がポジティブに変化していくことで、会社全体のマインドセットを良い方向へ導けると思いました。従業員が本来持っている潜在能力を掘り起こし、それに気付かせるきっかけとして有効な手法ですね。」
米国で開発された学修評価の基準の作成方法であり、評価水準である「尺度」と、尺度を満たした場合の「特徴の記述」で構成される。記述により達成水準等が明確化されることにより、他の手段では困難な、パフォーマンス等の定性的な評価や、質的評価、直接評価に向くとされ、 評価者、被評価者による標準化等のメリットがある。
文部科学省
Q6. 来年度、受講を検討されている皆さんへ一言お願いします。
志水氏「本プログラムでは、新事業創出に必要な知識だけでなく、心技体に通じる多くのことを学ぶことができます。豊富な講師陣による多角的な講義内容に加え、現場でのフィールドワークを通じた自分自身の気持ちの変化や、グループワークによる組織体質などを学べる良い機会だと思います。ぜひ、受講してみてはいかがでしょうか?」

